様々な経験を積むことで成長できる
所属プロジェクト:地域発信プロジェクト(取材:2024年度)

横畠 佑馬さん
広島県・加計高校
●プロジェクトに参加したきっかけは?
高校時代に生徒会に所属し、地域活性化のため地域の祭りの運営スタッフを務めたり、少子化改善のための政策を役場に提案したりといった活動をしていました。その時に地域のために活動することの楽しさを知り、地域の人の笑顔を見ることにやりがいを感じました。そのため、大学でもそのような活動ができないかと思っていたところ、プロジェクトメンバー勧誘期間に「地域発信プロジェクト」の当時のリーダーから、地域とたくさん関わることができるという話を聞き、またその熱意に押されて参加を決めました。
●プロジェクトの活動で印象に残ったことや学んだことは?
私が興動館プロジェクトにしかない魅力だと考えるのは、様々な活動の中で多様な価値観に触れ、その自分の価値観との違いを認めて受け入れることで視野を広げることができるということです。
地域発信プロジェクトは、祇園地区の特産品を発信し、地域を活性化させることを目的としています。そのため、地元の農家の方々や商工会、企業などと連携して活動しています。
私たちは祇園の特産品である「祇園パセリ」を発信しようと、生産者の方に勉強会を開いていただきました。その際に、祇園パセリは「食べることを目的としたパセリ」として生産されているということを知りました。これまでの私が思っていたパセリは「スープにふりかけてあるもの」「パスタのソースに使うもの」「お皿の隅で彩りを添えるもの」といった料理を引き立てる名脇役という認識で、メインで食べる物、つまり主役というイメージはありませんでした。しかし、苦みが少なくほのかに甘みが感じられ、そのまま食べてもおいしい祇園パセリによって、その固定観念がひっくり返され、そのおいしさに衝撃を受けました。この勉強会を通して、物の用途や、価値を決めつけないことで、自分自身の視野が広がっていくと感じることが出来ました。
私は、このプロジェクトで2年間リーダーを務めました。その中で、メンバーと価値観の違いでトラブルが起きたことがあります。私が相手のためにと思い発言したことがきっかけで、不信感と嫌悪感をあらわにされてしまいました。私はなぜなのか理由がわからず、それからそのメンバーと意見の食い違いが多くなったことから、私自身も嫌悪感を抱くようになってしまいました。そして、いま考えると情けないことなのですが、そのメンバーに対して無関心な態度をとるようになりました。しかし、このままではプロジェクト全体に悪い雰囲気が伝わり、全員で良い活動ができないと思い直し、勇気を出してそのメンバーと本音で話す機会を設けました。その時にはじめて、そのメンバーの「自分の考えを否定されたと感じていた」という気持ちを知りました。本音で話をしたことによりお互いのわだかまりも消えて、今ではとても良い関係を築けています。このことから、自分の考えをただ伝えるのではなく、きちんとコミュニケーションをとることでお互いの価値観を理解し、認め合うことの大切さを痛感しました。また、このことがきっかけで他のメンバー達との関わり方も意識するようになりました。それにより、プロジェクト全体で以前よりも活発に意見交換ができる雰囲気をつくることができたのではないかと思っています。
この2つの経験から、自分の考えが全てだという勝手な価値観にとらわれないよう、物事を多面的に見たり相手の考えを受け入れて大切にしたりすることを意識するようになりました。
●この学びを今後、どのように活かしていきますか?
社会に出た時には、価値観の違いに驚き悩むことが必ずあると思いますが、その時にプロジェクトで学んだことを生かして、価値観の違いを受け入れ、自分にはなかった新たな視点として前向きにとらえていきたいです。
私は将来、営業職に就きたいと考えています。プロジェクト活動での学びを念頭において、お客さまに一方的にサービスを押し付けるのではなく、お客様の意向も聞きながら、より良いサービスを提供できる営業マンになりたいと思います。
国境を越え、自分の殻を破れたから成長できた
所属プロジェクト:インドネシア国際貢献プロジェクト(取材:2024年度)

橋本 悠李さん
広島県・広島県立広島商業高校
●プロジェクトに参加したきっかけは?
私は小さいころから海外の文化に興味があり、その中でも特にアジア雑貨に魅力を感じていました。高校生の時に広島経済大学のオープンキャンパスに参加した際、インドネシア国際貢献プロジェクトの説明ブースで、アジア雑貨に触れることができると同時に海外渡航できるチャンスがあることを聞き、入学後にすぐ参加しました。
●プロジェクトの活動で印象に残ったことや学んだことは?
インドネシア国際貢献プロジェクトは、「伝統工芸品を使ったビジネスモデル」を確立することで、生産者の生活水準の向上と伝統継承を行うことを目的に活動をしています。私たちが着目したのは、インドネシアの伝統工芸品であり、生産者たちが大切にしているにもかかわらず、代替品に取って代わられることで忘れられかけている「テヌン」という布です。テヌンはとても丈夫で、様々な柄の一つひとつに意味がある、とても魅力的な布です。
私の初めての渡航は、テヌンを使用したオリジナル商品の開発や現地企業と協力した技術支援のほか、生産者の住んでいる村の調査などが目的でした。
実際に現地の村を訪れましたが、私は英語が全く話せなかったため、生産者の方々と通訳を介して会話をしていました。しかし、通訳を介しての会話ではこちらが聞きたいことの細かいニュアンスまで村の方に伝わらず、テヌンを再び広めていきたい理由をうまく聞き出すことができませんでした。求めていた返答が得られないことで、この人たちは何をしたいのか、私たちは具体的にどのように関わればよいのかがわからなくなり、プロジェクトの活動自体に自信が持てなくなってしまいました。
このままでは活動の目的を見失ってしまうと思った私は、現地の人のニーズをきちんと把握するために、まずは語学力を身につける必要があると考えました。そのため、日本に帰国した後、英語やインドネシア語の授業を履修することに加えて、自宅学習も行いました。その結果、半年後に再びインドネシアに渡航した際には、少しだけですが英語で会話することができるようになりました。それだけではなく、私のつたないインドネシア語でも現地の方が真剣に耳を傾けてくださることから、勇気を出して積極的に現地の方たちとコミュニケーションを取りました。その結果、前回渡航ではできなかった、インドネシアの人たちと交友関係を結ぶことができました。特に、現地で共に活動してくれる本学提携校のガジャ・マダ大学の学生とは、帰国してからも連絡を取り合っています。これにより、現地での活動をスムーズに行えるようになっただけでなく、日本での活動にも常にインドネシアの人たちの声を聞きながら、その人たちのために思いを持って取り組むことができるようになったと感じています。
私はインドネシアでの活動を経験したことで、語学力に自信がないからが話さないではなく、少しでも良いから英語や現地の公用語を話す努力をすることや、自分から積極的にコミュニケーションをとることが、人と人との関係性を深める大切な一歩になることを学びました。
●この学びを今後、どのように活かしていきますか?
私は将来、海外進出している日本の企業に就職したいと考えています。そのために、英語を流暢に話せるように勉強していきます。まずその一歩として、語学力を磨くと同時に外国人の価値観や文化が理解できるよう、留学を視野に入れています。
私は入学前、「海外に興味はあるけれど、自分は日本でしか働けないんだろうな」というあきらめと先入観がありました。しかし、大学入学後にプロジェクトに参加し、インドネシアに渡航したことで、コミュニケーションの壁にぶつかり、それを乗り越える経験をすることができました。この経験が自信になり、またインドネシアの人と交流を深める中で、今では海外をより身近に感じ、「私でも海外で働ける、働きたい」と思うようになりました。
これからも、勇気をもって積極的に行動することで自分自身の殻を破りながら、挑戦し続ける人間になりたいと思います。
応援してくれる存在が成長するきっかけになる
所属プロジェクト:地域発信プロジェクト(取材:2023年度)

吉本 あいさん
広島県・広島国際学院高校
●プロジェクトに参加したきっかけは?
私は小さいころ、路面電車が好きでした。家族で電車に乗ってお出かけすることにワクワクしましたし、いろいろな形の電車を見ているのも楽しかったからです。ある日、路面電車に乗っていた私は、外国からの観光客にとても親切にしている運転手さんに出会いました。優しくてかっこいい運転手さんは私の眼にはヒーローに映り、ますます大好きになりました。
広島の代表的な乗り物であり、広島市民や旅行客などを乗せて走る路面電車は、広島の活性化に大きな役割を果たしています。また、原爆投下わずか3日後から再び広島の街を走り始めた路面電車は、広島市民を大いに勇気づけた復興の象徴であり、誇りでもあります。
高校生になり、こうしたことがわかるような年齢になったとき、漠然と「私も広島の活性化に貢献できる仕事をしたい」と考えるようになりました。
大学入学後、いろいろなプロジェクトを見学している中で「地域発信プロジェクト」を知り、このプロジェクトで活動すれば、将来の夢のために必要な力を身につけられるのではないかと思い、参加しました。
●プロジェクトの活動で印象に残ったことや学んだことは?
地域の特産品生産者とそれを商品化する企業を私たちがつなぐことで、新しい商品が生み出されていく過程がワクワクして大好きです。その商品を私たちの手で販売し、手に取っていただいた方の反応を直接見ることができたのは、地域の魅力が伝わったという喜びを感じる貴重な体験になりました。
この活動をしていくなかで、私たちの未熟な提案に真剣にアドバイスをくださったり、快く協力していただけたりするなど、地域の方々の愛情や優しさを感じる場面が多々ありました。このことから、私たちが全力で活動できるのは、これまで地域の方々と良好な関係を築いてこられた先輩たちのおかげだと気づきました。先輩たちが良好な関係を築いてくれたからこそ、プロジェクトを応援してくださる方々の協力を得ながら生産者と企業をつなぐ活動ができ、地域に誇れるものを生み出す活動ができるのだと学びました。
この学びから、物事を成し遂げる第一歩として、まずは人と人との良好な関係を積み重ねて、続けていくことが大切であることを学びました。
●この学びを今後、どのように活かしていきますか?
これからも、目の前の方との良好な関係を積み重ね、多くの方々とつながりを大切にしていきます。そして、今後は私も誰かの夢を応援できる人になりたいと思います。
この経験と学びを活かしながら、「広島の活性化に貢献できる仕事」をしたいという夢を叶えるために、誰もが誇れる広島の姿をイメージしつつ、歩み続けたいと思っています。
「なんのため?」行動の意味を考えるようになった
所属プロジェクト:祇園から食品ロスなくそうプロジェクト(取材:2023年度)
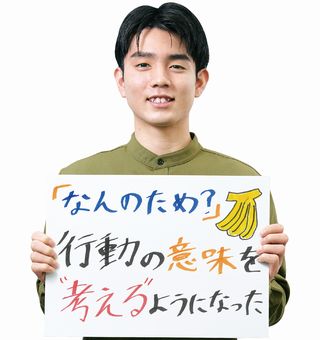
繁浪 駿汰さん
島根県・出雲商業高校
●プロジェクトに参加したきっかけは?
高校時代にSDGsについて学んだことで社会貢献に興味を持ち、実際に何かに取り組んでみたかったのですが、その機会がありませんでした。大学入学後に、興動館が主催する「新規興動館プロジェクト立ち上げ説明会」に参加した際、食品ロス削減の取り組みのアイデアをお聞きし「これだ」と思ったのと、新しく自分たちで何かを始めることの魅力も感じたので、2021年度にリーダーとしてこのプロジェクトを立ち上げました。
●プロジェクトの活動で印象に残ったことや学んだことは?
人が生活する上で「食」は必要です。だから食品ロス削減に関する活動を幅広く考えることができるのが面白いと思いました。これまで、大学のある祇園地区に住む方々を対象として食品ロス削減の意識向上を目指したオリジナルすごろくやクイズを実施するイベントに取り組んできました。今後は、祇園に住む方々のうち私たちのような若い世代に対象を絞って、取り組んでいきます。私もそうなのですが、若い世代の方々は料理を作ることに慣れておらず、食材を無駄なく使うノウハウが少ないことから、食材を使いきれるレシピの紹介などの食品ロス削減に向けた啓発を行う予定です。また、新たに農家の方や子ども食堂などを支援している団体と連携して、啓発だけでない食品ロス削減に向けた活動も考えています。
この活動に取り組むことで、私自身もスーパーに陳列されている食材は前から取ったり、必要なものだけを買ったりするようになりました。この、「必要なものかどうかを考える習慣」は、食材を購入する際だけではなく、リーダーとしてメンバーと一緒に活動するうえで「何のために行うのか?」「本当に必要なことなのか?」を自然と考える習慣につながったと思います。
●この学びを今後、どのように活かしていきますか?
プロジェクトを立ち上げる前の私は、与えられたことだけをやることが多く、自分が取り組んだことがどうなるかまでは考えずに生活してきました。ですが、プロジェクト活動に取り組んだことで「何のために行うのか?」を普段から考える力がついたことで、一つひとつの行動の意味を理解するようになりました。行動の意味を理解すると、やる気やモチベーションが上がってきますし、「次に何をすべきなのかの手がかり」が見えてくると思います。
まだ将来の具体的な進路は決めていませんが、今後のプロジェクト活動を通して見つかるであろう手がかりを頼りに、自分を信じて後悔の無い選択をしたいと思います。
自分の変化を実感できる!!
所属プロジェクト:インドネシア国際貢献プロジェクト(取材:2022年度)

濱岡 咲希さん
広島県・広島市立広島商業高校
●プロジェクトに参加したきっかけは?
日本と海外の違いに興味はありましたが、英語が苦手なことから、言葉が通じない外国人に対して「怖い」印象があり、行動に移すことはありませんでした。
大学に入学後、プロジェクト勧誘イベントで楽しそうにプロジェクト活動について語っている先輩を見て、自分もこのプロジェクトに参加すれば、日本と海外の違いを知ることができるかもしれないと思ったため、参加を決めました。
●プロジェクトの活動で印象に残ったことや学んだことは?
1年生の夏にインドネシアに渡航した時、支援をしている村の方々へ商品に付加価値をつける技術支援を行いました。新しい技術が得られることで可能性が広がることを実感し、笑顔になっている村の方々を目の当たりにし、私達の活動は「明るい未来のイメージを持つことを手助けする」ことなのだと肌で感じました。
その初渡航時に、私達の活動に協力してくれている姉妹校のインドネシア人学生に初めて出会いました。しかし私は、英語への苦手意識からコミュニケーションを取ることができませんでした。しかし、インドネシア人学生は、英語が苦手な私を理解してくれて、身振り手振りで好きな日本の歌や漫画などを教えてくれました。共通の話題で盛り上がることができ、友達になることができました。外国なので、言葉や習慣、文化は当然違いますが、共通する部分もあります。それを見つけることができれば、友達になれるということを教えられました。それからは、外国人に対する苦手意識が無くなったと同時に「もっと英語を使って友達の言葉を理解したい、そしてインドネシアの未来について語りたい」と思うようになりました。この思いを達成するために、プロジェクトメンバー向けの英語の勉強会を提案し、プロジェクトメンバー全員で取り組んでいます。まだ成果を実感できるところまできたわけではないですが、この勉強会を今後も続けていくことが、インドネシアの幸せにつながると信じています。
●この学びを今後、どのように活かしていきますか?
以前までは、自分と他人の違いを受け入れることができずに、少数の仲の良い友達とだけ話していました。しかし、今は色々な人と話をして、自分と違うところを知りたいと思うようになりました。これは、プロジェクト活動を通しての変化であり成長だと思います。今後も、違いを恐れずに、むしろ違いを知ることを楽しんで人間関係を広げていきたいと思います。このプロジェクトを経験したことで、将来は多くの人と関わりながら「明るい未来」を共につくっていく仕事に挑戦したいと思うようになりました。
やってみよう!その一歩から「なりたい自分」に近づける!
所属プロジェクト:所属プロジェクト:スポーツによる地域活性化プロジェクト(取材:2022年度)
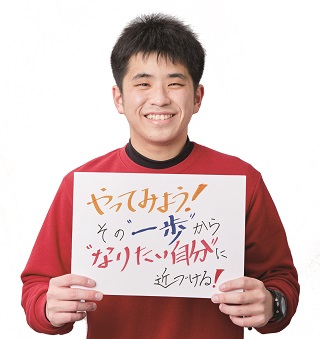
前田 健太郎さん
鹿児島県・尚志館高校
●プロジェクトに参加したきっかけは?
私はこれまで、スポーツ選手として様々な大会に参加してきました。競技を引退した後、次は何をやろうかなと考えたとき、今度は大会で見てきた「スポーツを支える側の立場」としてスポーツに関わりたいと思いました。そこで、スポーツイベントの企画や運営などを経験できる「スポーツによる地域活性化プロジェクト」に参加しました。
●プロジェクトの活動で印象に残ったことや学んだことは?
1年生の時の「サンフレッチェ広島応援イベント」に運営メンバーとして参加した際に、参加者の楽しむ姿を見て、イベントを「支える立場」の楽しさに気づきました。そのため、2年生になった時「サンフレッチェ広島応援イベント」のイベントリーダーに挑戦することにしました。しかし、イベントを企画する時期にちょうど新型コロナウイルス感染症の感染が拡大したこともあり、活動が制限されていく中でメンバーのモチベーションはどんどん下がっていきました。自分自身はこれまでの経験から、イベントを楽しむ人達の笑顔を想像することでモチベーションを高めながら準備を行っていましたが、参加者の笑顔に触れた経験のない(少ない)メンバーのモチベーションは一向に上がりません。自分は元々「やれ」と言われて「やらされる」ことに抵抗があり、大学の授業でも「一人ひとりがやりがいを感じて行動することが大切である」と学んできました。そこで、無理やりやらせる方法よりも、イベントを経験したことがない後輩メンバーに「やりがい」を感じてもらうにはどうすればよいかを考えました。そこで私が出した結論は、自分から「こまめに感謝の気持ちを伝えること」でした。人に喜んでもらうことの「やりがい」を感じてもらえれば、私と同じようにそれが本人のやる気につながるのではないかと考えたからです。そこからはメンバーに「ありがとう」の気持ちを積極的に伝えながらイベントの準備を進めていきました。その結果、メンバーも自分から行動してくれるようになりました。イベント当日は、全員が役割と責任を果たしてくれたことで、会場は大いに盛り上がり、来場者に喜んでいただくことができました。
私が学んだことは、様々なことを客観的に考えることの大切さです。例えばイベントを企画するとき、過去の自分は「自分がやってみたいから」など自分本位な考えでアイデアを出すことがありました。しかし、これまでの活動を通して、イベントの目的・目標・参加者のニーズなどを念頭に置いて客観的な視点で企画することが大切だと気付きました。今では、アイデアを考えるときは「参加者にとって必要か」「目的・目標に沿っているか」など一呼吸おいて考えられるようになりました。また、振り返りの重要性にも気づきました。イベントを運営し、良かったことや気づいたこと、改善するべき点を振り返り、次に生かすことを意識するようになりました。
興動館プロジェクトには、様々なことに挑戦する“一歩”が踏み出せる環境があり、多くの人と人間関係を築ける機会があります。何かをやってみたい学生には一番にオススメしたいです。
●この学びを今後、どのように活かしていきますか?
今後、学生生活の中でも常に振り返りを意識し、自分自身を客観的に見つめ直すことで、成長を続けていきたいと思います。
理解し合える仲間ができる!
所属プロジェクト:宮島の魅力を発信したい学生プロジェクト(取材:2022年度)

佐々木 奈乃さん
島根県・松江南高校
●プロジェクトに参加したきっかけは?
将来は地元に貢献する仕事に就きたいと考えており、地域活性を行うプロジェクトに興味がありました。1年生の時、当時のリーダーに「自分も地方から入学したけど、将来は地元に貢献したいと思っている」と自分の考えに共感してもらったことがきっかけで、プロジェクトに参加しました。
●プロジェクトの活動で印象に残ったことや学んだことは?
行政から地域活性を行っている団体への助成金事業に応募することになり、プロジェクトリーダーとして申請書の作成に関わることになりました。書類を作成する期間が2週間程度と短いため「応募してみないか」と声がかかった時は正直「完成できない」と思いました。それでも、助成金申請は自分にとって初めての経験だったため、失敗したとしても経験になるので「できなくてもいいからやってみよう」と思っていました。そう思いながら、メンバーに申請書作成希望者を募ったところ、1,2年生を中心に6名が手を挙げてくれました。新型コロナウイルス感染症の影響でプロジェクト活動に制限があり、ほとんど何の経験もない1,2年生達が手を挙げてくれたことに正直驚きました。それと同時に、メンバー達に経験が少ないことを理由に「やっぱりできなかった」と思ってもらいたくないと強く思いました。そこから、助成金申請書作成は「できなくてもいい」から「みんなと一緒にやりきる」に考え方が変わりました。それからは、申請書の完成を目指し、1,2年生だからという考えを捨てて、みんなで作成に取り掛かりました。通常のプロジェクト活動に加えての申請書作成でみんなの負担は増えましたが、文句を言わずに最後までやり切ってくれたことに感謝しています。また、申請書の作成を通じて、宮島の隠された魅力や現状を発信する活動が、宮島とどのようにつながっているのかを理解することができました。残念ながら助成金は獲得できませんでしたが、一人だと取り組む前から「できない」と諦めることでも、「みんながいればできる」ことを実感しました。
昔の自分は、自分の考えが正しいと思うあまり、他人からの指摘を素直に受け入れることができませんでした。しかし、同じ目的に向かって真剣に考えるからこそ、自分の考えに対し、色々な視点で指摘をしてくれるメンバー達がいることに気づきました。それに気づいてからは、相手の発言の意味を考え、考え方の違いを受け入れながら、議論できるようになりました。理解し合っているがゆえに、時にはぶつかることもあるけれども、共に考え、乗り越える回数を重ねたことで、何でも言いあえる一生の仲間を得ることができたと感じています。
●この学びを今後、どのように活かしていきますか?
卒業後は地元に帰ります。このプロジェクト活動で得た学びを生かして、理解し合える仲間をつくり、たくさんの人と力を合わせて地元の活性化に貢献していきたいです。
一人では限界がある。
みんなと共に考え、進めた方がはるかに良いものができると分かりました。
所属プロジェクト:カンボジア国際交流プロジェクト(取材:2021年度)
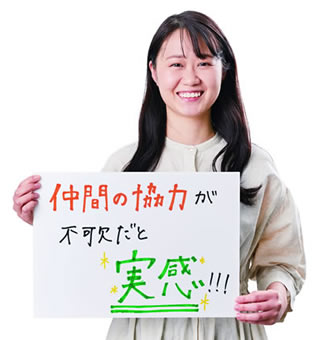
佐藤 真梨子さん
岡山県・総社高校出身
●プロジェクトに参加したきっかけは?
海外へ行ってみたいという思いを持ちながらプロジェクトを見学する中で、「カンボジア国際交流プロジェクト」の海外での教育支援という活動内容に魅力を感じ、参加を決めました。
●プロジェクトの活動で印象に残ったことや学んだことは?
私は、カンボジアの子ども達が授業で使用する副読本を作成する部署のリーダーを務めています。「私の代で完成させたい」との焦りもあり、一人で考えてメンバーに指示をした方が早いと考え、ほぼ一人で作業を進めていました。その結果、メンバーが会議に来なくなるなど部署としてまとまりに欠けてしまい、私自身も孤立し悩んでいました。そんな私を見かねた興動館の職員さんが「みんなと進めることが大事だよ」というアドバイスをくれました。そこで勇気を出してメンバー一人ひとりに相談したところ、全員が活動を自分事としてとらえ、部署全体で製作が進むようになりました。みんなが積極的に意見を出してくれるようになったことで、内容も充実したものになりそうです。この経験から、物事は一人で抱えず、みんなを頼り、一緒に考えることが大切だと学びました。
●この学びを今後、どのように活かしていきますか?
現在も、この新しい副読本がカンボジアの子ども達に夢や希望を与えられる一冊になるよう、製作を進めています。プロジェクト活動で得た学びを活かし、メンバーそれぞれの意見や考えを理解し尊重しながら、リーダーとしてチームをまとめ、本を完成させたいと思います。完成後は、この副読本を使用した授業を私たちが現地で行い、カンボジアの子ども達が自らの国の将来を考える「最初の一歩」をサポートしていきたいと思います。
目先の活動にとらわれることなく、
最終的なゴールは何かをイメージするようになりました。
所属プロジェクト:子ども達を守ろうプロジェクト(取材:2021年度)
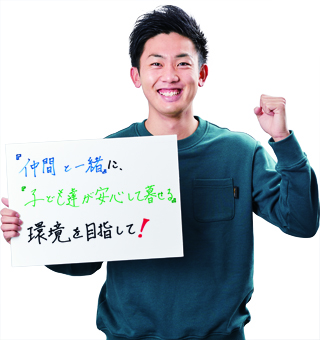
梶白 航平さん
広島県・忠海高校出身
●プロジェクトに参加したきっかけは?
子ども達が安心して暮せるまちづくりを目指している「子ども達を守ろうプロジェクト」に参加したのは、私自身が小さいころに地域の人に優しくしてもらった楽しい思い出があったからです。私も同じように、子ども達のために何かできたらと思い、このプロジェクトに参加しました。
●プロジェクトの活動で印象に残ったことや学んだことは?
子ども達と信頼関係を築くことを目的として開催したスポーツ大会で、子ども達から「面白くない」「やりたくない」と批判を受ける出来事がありました。私は、進行することに注力するあまり深く考えずにリレーのチーム分けをしていたのです。その結果、足の速い子どもが集まるチームができていたのに気付きませんでした。信頼関係を築くはずのイベントで、子ども達から不信感を買ってしまう大きな失敗でした。このことから、ただイベントを開催すればよいということではなく、目的を達成するためには、対象者である子ども達のことを1番に考えることが大切だと改めて学びました。
●この学びを今後、どのように活かしていきますか?
地域の方々やプロジェクトの先輩たちが紡いできた「子ども達が安心して暮せるまちにしたい」という想いを、私たちも後輩たちに引き継いでいきたいと思っています。そのために、私と同じ失敗をしないよう、常に対象者である子ども達のことを1番に考えることの大切さを伝えていきます。また、私はこれから就職活動を控えていますが、プロジェクト活動で経験したことや学んだことを強みや自信として、社会に出てからも頑張っていきたいと思います。