実社会で無から有を生み出せる人材に
履修科目:企画力養成講座(企画力フィールド)(取材:2024年度)
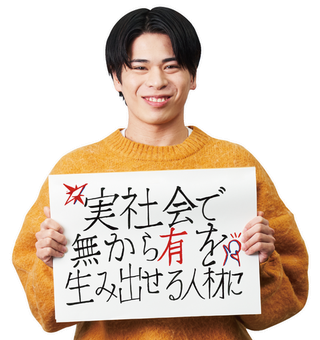
山口 慶典さん
広島県・広島県瀬戸内高校
●履修したきっかけは?
私は「『ゼロから立ち上げる』興動人※」になるためには、無から有を生み出すための企画力が必要だと考えています。この授業のシラバスでは、企画力を構成する様々なスキルについて例題を用いて解決しながら学ぶと記載されていたため、私が求めている企画力を養える環境だと思い履修しました。
●履修して印象に残ったことや学んだことは?
この授業では、自由な発想から生み出されるアイデアや意見を決して否定することはなく進められます。また、アイデアや意見を出して終わりではありません。アイデアを形にするときに起こる問題を解決しながら一つの形にしていくために、問題を具体的に解決するための論理的思考法であるMECE(Mutually(お互いに)、Exclusive(重複せず)、Collectively(全体に)、Exhaustive(漏れがない))を学びました。このMECEは実社会、主にコンサルティング業界で実際に用いられている思考法で、学生から出たアイデアや意見についてMECEを用いて問題解決策を考えることが初めてだったので、とても面白いと思いました。
私はこの授業を受ける前までは、社会課題を解決するには、やるべきことは一つだけしかないと思い込んでおり、自由な発想やアイデアで出てくる多くの方策では解決できないと決めつけ、自ら提案することをやめるばかりか、他者の意見にまで否定的になっていました。それには、自分の提案が間違っていたらどうしようという不安も含まれていました。授業を受けた当初も、自由な発想は現実味に欠けることから、形にすることは難しいと思っていましたが、MECEを用いて形にしていくメソッドを学んだことで、多くのアイデアを形にすることができました。この形になった時の嬉しい感情と同時に、自由な発想から形にしていくことは無理だと諦めていた自分に気づき悔しさもありました。
このことから私は、自由な発想や意見を否定的に見ず、多様性を理解して進めていくことや、形にしていく段階で問題点が見つかるごとに一つずつ対応すれば、社会課題の解決に近づいていくことができると学びました。
●この学びを今後、どのように活かしていきますか?
私は興動館プロジェクトの一つである「スポーツによる地域活性化プロジェクト」に所属しています。
プロジェクト活動をする中で、活動について話し合う機会や企画の立案など、多くの場面でアイデアを出して終わりという状態が見受けられます。自由な発想や意見は企画するための大切な材料なので、この授業で学んだ企画力を活かし、プロジェクトの会議の際にメンバーから出てきたアイデアを否定的に見ず、アイデアを形にしていく際に出てくる問題点はMECEを活用しながら解決し、形にしていきます。
また、卒業後、実社会で無から有を生み出し、形にしていける人材になるために、他者理解を深め、共に形にしていくことを忘れずに、行動し続けていきたいと考えています。
「真実」の自分を知ることで元気になれる!!
履修科目:禅(ZEN)で元気なこころとからだをつくろう(元気力フィールド)(取材:2024年度)

NGUYEN THUY DUさん
ベトナム・広島YMCA専門学校
●履修したきっかけは?
私はベトナム出身で信仰している宗教はキリスト教のため、自分を振り返ったり見つめたりするよりも神様とのつながり、神様の考えを大切にしています。この授業のシラバスを見ていると、坐禅の実習を通し、自らの「こころ」を見つめることができるとありました。自分とは違う宗教に触れ、自分のこころを見つめるとはどういうことなのか気になったため履修しました。
●履修して印象に残ったことや学んだことは?
この授業では坐禅の実習を通し、自らのこころを見つめ現代を生き抜くちからを身につけることを目指します。
私は、普段の生活では、母国とは異なる国での授業やアルバイトが多忙なため、自分自身に向き合うことができていませんでした。しかし、この授業で初めて坐禅を組む体験をした際に、自然と自身の行動を振り返ることができました。
アルバイトではお客様に気持ちの良い接客だと思ってもらえる仕事ができているか、また、日々多忙で余裕の無さから友人への連絡をおろそかにしていないかなど、自身と向き合うことで、「自分の周りにいる人を大切にしたい」と思う自分がいることに気づきました。
それ以降、アルバイトではこれまで以上に笑顔で気持ちの良い接客を心掛けるようになりましたし、友人たちと接するときにも「自分だったらどういう接し方をされたら嬉しいか」を意識するようになりました。その結果、周りの人たちから「グエンの笑顔のおかげで元気が出たよ」と声をかけてくれることがありました。
●この学びを今後、どのように活かしていきますか?
私はこの授業を通して、坐禅を組むことで自分と向き合い、自分が大切にしていることに気づくことができました。この気づきが、自分だけではなく周囲の人々にも良い影響を与えることができたことは、とてもうれしい体験となりました。
これらはすべて、自らの「こころ」を見つめることができたからこそだと思います。
私は今後も自分と向き合い、自身を客観視し、前向きに物事を考え、心に余裕を持つべく、1週間に1回は自分と向き合うために坐禅を組む時間をつくりたいと思います。
伝わる喜びを感じられる!
履修科目:瀬戸内海地域の魅力を発信しよう(元気力フィールド)(取材:2023年度)
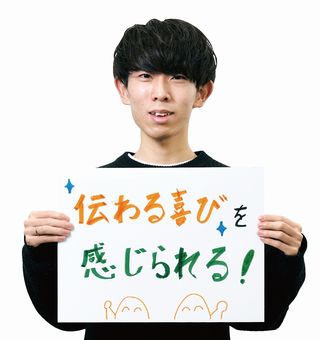
上﨑 世界さん
広島県・可部高校
●履修したきっかけは?
以前、瀬戸内海について聞かれた時、答えることができませんでした。広島で生まれ育った私が知っていると思っていた瀬戸内海のことが、実は何も知らないことにショックを受け、少しでも知りたいと思い受講しました。
●履修して印象に残ったことや学んだことは?
この授業は、瀬戸内海地域の食や文化などの魅力を調べて発表をする内容になっています。同じテーマでも、一人ひとり発表する視点が異なり、自分にはない伝え方をしているのが刺激になりました。私は観光をテーマにして、外国人旅行客を対象にした発表をすることになりましたが、瀬戸内海地域のことを知らない私が、同じように知らない人に魅力を伝えることができるのか悩みました。悩んだ結果、瀬戸内海地域のことを知らない自分だったら何を知ると興味を持つかを常に考えながら準備を進めました。地域のことや魅力をイメージするには、風景写真だけでなく、住んでいる方や訪れる観光客の推移など具体的な情報があるとよりイメージしやすいと思い、一つの資料だけに頼らず、様々な視点から情報を集めて発表に盛り込みました。その結果「背景や情報が詳しく語られているから、何を伝えたいかわかりやすい。」という評価をいただき、伝わる喜びを感じると共に、伝え方のコツを学びました。
●この学びを今後、どのように活かしていきますか?
これまで私は、会話の際に「相手も知っているだろう」と思って会話をしていました。そのため、思ったほど伝わらないと感じることもありました。この授業の受講後「相手と同じイメージになるためには何を伝えるか」を意識して会話をするようになりました。その結果、自分の考えが伝わることが多くなり、理解してもらえることが楽しくなりました。
これから始まる就職活動では、人と直接関わる仕事に就きたいと思っています。この授業で得た学びを活かし、相手と同じイメージになることを意識して関わっていきたいです。
「今」だけではなく将来に活きる「力」
履修科目:興動館プロジェクトの経営戦略(行動力フィールド)(取材:2023年度)

伊藤 絢音さん
広島県・呉宮原高校
●履修したきっかけは?
2年生の時、所属しているスポーツによる地域活性化プロジェクトでイベントの主担当になったのですが、どのようにプロジェクトをまとめ、企画を進めていくのが良いのか最後まで悩みながら取り組んでいました。その後、プロジェクトの副リーダーになったことをきっかけに組織運営について詳しく学びたいと思い履修しました。
●履修して印象に残ったことや学んだことは?
この授業は興動館プロジェクトに所属している人が多く履修しており、「興動館プロジェクトではどのように成果を上げていくか」という視点で各プロジェクトの現状から問題点を分析し、これから取り組むべき課題をグループで考えていく内容になっています。私は、1年生の時からプロジェクトに所属しているので、目標や取り組むべきことは理解しているつもりでした。しかし、活動によって「対象者へどういう影響があるのか」「自分たちにはどういう成長があるのか」などを改めて考えた時、考えがまとまらないことがありました。その時、「自分たちのやりたいことだけをやっていた」ということに気付きました。そこから、KPI分析やロジックツリーなどさまざまな分析手法を学んだことで、目的や目標が整理され、これまで漠然としかイメージできていなかったプロジェクトの課題やこれから取り組むべき行動を明確にすることができました。
●この学びを今後、どのように活かしていきますか?
「なぜこの活動をするのか」ということをプロジェクトという組織全体で正しく理解しながら進めていくためにも、この授業で学んだロジックツリーなどのフレームワークをプロジェクトメンバー全員で行います。一人ひとりが目的と目標を明確化し、取り組むべきことを意識して活動するプロジェクトになるように働きかけて行きます。
そして、この学びをプロジェクト活動だけで終えるのではなく、自分自身の夢であるスポーツ関連の仕事に就くために今自分が何をすべきなのかを考え、将来を意識した行動を取ることにも応用して行きたいです。
挑戦するきっかけがココにある!
履修科目:ライフプラン(人生設計)でやる気づくり(元気力フィールド)(取材:2022年度)
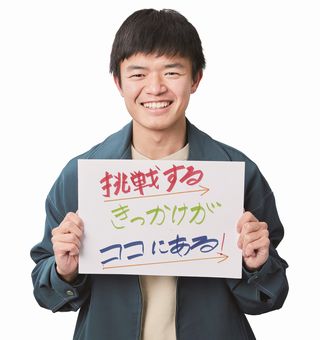
三好 栄輔さん
広島県・広島県立広島商業高校
●履修したきっかけは?
高校生の時から、投資や資産運用に興味があり、自分なりに調べていました。この授業を通して、自身のライフプランをイメージすることと、それに基づいた資産運用の知識を身につけたいと思い受講しました。
●履修して印象に残ったことや学んだことは?
「ライフプラン(人生設計)でやる気づくり」の魅力は、興動館科目の特徴である「双方向」を強く意識した、教員と学生が共に授業を盛り上げていく一体感だと感じます。担当の倉橋先生が学生一人ひとりの個性を尊重して接してくださることにより、授業中に感じた疑問や意見を自由に発言できる雰囲気がありました。さらに、グループワークが多いことで、学生同士で意見を出し合う際に積極的に発言ができるようになりました。
この授業を履修したことで、相手に自分の意見をきちんと伝えること、相手が安心して話してもらえる場づくりをすることといった「コミュニケーション能力」の重要性に改めて気づき、意識するようになりました。
●この学びを今後、どのように活かしていきますか?
私はこれまで、面白い話をしなければいけないのではという思いに縛られ、友人にさえ自分から話しかけることためらうほどでしたが、授業やグループワークなど話すテーマが決まっている場面では、積極的に発言することができました。これは自分にとっては発見であり成長であると感じています。
自分の思い描く理想のライフプランを現実のものとするためには、他者と関わることは必要不可欠です。自分に合った「コミュニケーション」とは何かを探しながら、これからは積極的に人と関わっていきます。
苦手な自分に向き合い、それを乗り越えるための行動を起こすことは大きな“挑戦”です。
この授業を受講したことが、一歩を踏み出すきっかけになりました。
今までの考え方が「変わる」
履修科目:身近なボランティア活動(行動力フィールド)(取材:2022年度)

VU LE HUONG LYさん
ベトナム・THAI PHIEN高校
●履修したきっかけは?
ベトナムの日本語学校に通っているときから、「人を助ける仕事」に就きたいと漠然と考えていました。そのイメージを具体化するために、ボランティアについても深く学びたいと考えて履修しました。
●履修して印象に残ったことや学んだことは?
この授業では、履修生が実際に活動されているボランティア団体を調べて発表する機会が多くあり、ベトナムのボランティアと日本のボランティアの違いを知ることができました。例えば、親のいない子ども達に対して食事を提供するボランティア活動についての発表を聞いた時、ベトナムにも同じようなボランティアはあると思いました。しかし、私の知っているベトナムのボランティアは、かわいそうな子ども達に食事を「与える」ことなのですが、日本のボランティアは、子ども達と一緒に料理を作って食べたり遊んだりすることだと聞き、物を「与える」ではなく「心に寄り添う」ところに大きな違いがあることを知りました。
「心に寄り添う」ボランティア活動や、日本語の能力に自信のない私の発表時に「がんばれ!」と応援してくれた日本人学生の優しさに触れたことで、ベトナムにいたころに抱いていた「冷たい」「仕事に厳しい」といった日本人のイメージが大きく変わりました。
●この学びを今後、どのように活かしていきますか?
これからは、実際にボランティア活動へ参加し、ボランティアの運営も含めた知識を深めたいと思っています。そして、ベトナムに帰国後は、山奥に住んでいて教育を受ける機会が少ない子ども達へ日本語を教えるボランティア団体を立ち上げたいと考えています。
この授業で学んだ、相手の「心に寄り添う」ことの大切さを、子ども達にも伝えていきたいです。
自分を知ることで、人との関わり方が変わった
履修科目:興動館プロジェクトとコミュニケーション(共生力フィールド)(取材:2022年度)
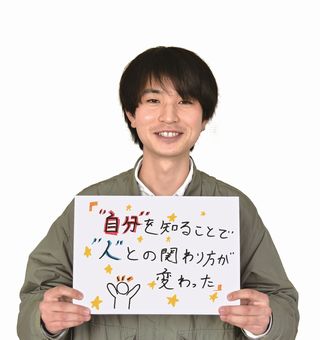
梶岡 尚大さん
広島県・呉高校
●履修したきっかけは?
2年の冬に「コミュニティFM放送局運営プロジェクト」のリーダーになり、会議の進行やプロジェクトメンバーとのコミュニケーションに課題を感じたため、本気で学びたいと思い履修しました。
●履修して印象に残ったことや学んだことは?
授業の序盤で行った「自己分析ワーク」を通して自分と向き合い、気付いていなかった自分を知ることができたことが、特に印象的で面白かったです。自己分析の結果が数値やグラフだけではなく、詳しい文章で表示されたことに加え、担当の志賀先生から、自分のタイプに適した役割や足りない点、意識すべき点をアドバイスしていただきました。そのおかげで、薄々感じていただけの自分の性格が明確になり、今後の改善点も認識することができました。
また、ただ聞いてメモを取るだけの一方的な授業ではなく、自分で考えたり、他の学生と話し合ったりする時間が多い授業スタイルだったので、元々自分の長所だと感じていた「主体性」がさらに高まったように感じています。
私はリーダーとして会議の進行をしていましたが、決めなければならないことに集中しすぎて、メンバーの様子に目を向けることができていませんでした。意思決定の際も、メンバーがほとんど発言しないので、ほぼ自分で決めてしまっていました。しかし、この授業を通して、自分が発言しやすい環境を作れていなかったことに気が付くことができました。そこから、「(効率を重視して)自分がやる」という考えから、「(チームとして成長するために)一緒にやる」という意識に変わりました。発言がないメンバーに「一緒に考えよう」と声を掛けたり、作業に積極的に参加してもらえない時は、個人の想いを尊重しながら役割を割り振ったりするなど、参加意欲が高まるような働きかけを行うよう意識したところ、少しずつプロジェクトの雰囲気も良くなったように感じています。
●この学びを今後、どのように活かしていきますか?
この授業で自分を知ったことで、今までの自分を中心とした人との関わり方から、相手の想いを尊重する関わり方に変わりました。この学びを活かし、プロジェクトのメンバーたちだけに限らず、私の周りにいる人たちの想いを大切にし、自分にできることは何かを考えながら生活していきたいです。
多角的な視点で考え、お互いを理解する心構えを持つきっかけになりました。
履修科目:広い世界に飛び出そう(共生力フィールド)(取材:2021年度)
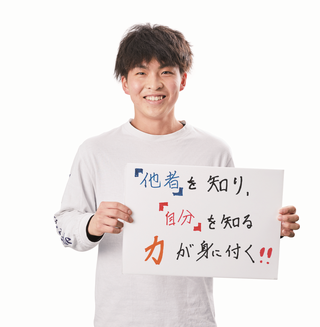
在間 貴大さん
広島県・神辺旭高校出身
●履修したきっかけは?
本学の外国人留学生とともに学ぶことで、コミュニケーション能力を身に付けることはもちろん、日本以外の国の知識をより深めることで自分の世界を広げたいと思い、履修しました。
●履修して印象に残ったことや学んだことは?
シンガポールにある姉妹校をインターネットで繋げ、お互いの国についてプレゼンをしあったことです。シンガポールは、やはり日本とは文化や価値観が違いました。しかし、質疑応答の際にお互いに恥ずかしがって手が挙がらない場面があり、国が違っても同じだなあと感じました。これまでは「海外と日本は違う」と思い込んでいましたが、「同じところもあれば、違うところもある」と考えが変わりました。この科目を履修してから、自分の世界を広げるには外国だけでなく日本のことも知る必要があると思うようになりました。これからますますグローバル化が進んでいく社会で活躍するためには、日本を知り、世界各国の文化や価値観をきちんと受け入れ、日本の文化や価値観だけが正しいと思わず、多角的な視点から物事を考え、お互いを理解することが大切だと学びました。
●この学びを今後、どのように活かしていきますか?
この科目を履修して、他国の文化であったり、価値観だったりをもっと深いところまで知りたいと思うようになりました。今後は、異文化に対する理解をもっと深め、グローバルな視点から物事を考えることができるようになりたいです。そのためには、なにより語学力が必要だと感じています。まずは英語力を高めて、もっと外国人と積極的にコミュニケーションが取れるようになりたいです。
「対象者のためになること」を意識し「今だからできること」を考える力がつきました。
履修科目:興動館プロジェクトと企画力(企画力フィールド)(取材:2021年度)

中山 瑞妃さん
広島県・安芸府中高校出身
●履修したきっかけは?
広島ハワイ文化交流プロジェクト」に所属していることから、プロジェクト活動の柱となる事業やイベントの企画の立て方を詳しく知りたいと思い、この科目を履修しました。
●履修して印象に残ったことや学んだことは?
ある課題が出た時、明るい雰囲気になればいいなという軽い気持ちで手描きのイラストを添えて提出したところ、先生から「何気なく描いたイラストに込められた想いが伝わり、企業のロゴになるケースもある。描いたときの気持ちを忘れずに大切にしてください」とアドバイスをいただきました。自分の気持ちが伝わったうれしさと、形にして表現することの大切さに改めて気が付きました。また、もう一つ印象に残っているのは、ネガティブをポジティブに変換するという話です。実際の事例を聞き、自分自身が感じる課題に置き換えて考えたことで「コロナ禍だから渡航できず、現地の方々と交流できない」という私の考えが「インターネットを使えば渡航するより多くの方々と交流できる」に変わり、ポジティブな企画を考えられるようになりました。
●この学びを今後、どのように活かしていきますか?
現在、ハワイの中高生たちとオンラインでつながるイベントの企画をしています。この授業で学んだ知識や考え方を他のプロジェクトメンバーとも共有し、「自分のやりたいこと」だけではなく「対象者のためになること」を意識した、コロナ禍だからこそできるポジティブなイベントにしたいと思っています。